
“踊絵師” 神田さおり 心を貫く空間表現に至るまでヒストリーから、現代を謳歌する生き方のヒントを探る part2
〜part1からのつづき〜
今回は、「踊絵師」としてアーティスト活動を行う、神田さおりさんにインタビューを行った。字で書いての如く、舞いながら全身で絵を描いていく。「独自のスタイル」と言うと在り来たりだが、オンタイムのパフォーマンス性と、それによって生み出されるアートワークの圧巻のクオリティは、他に説明を要らなくさせる凄みがある。
世界的に著名な国内外の数々の企業からのオファーを受け、華々しいアーティスト活動を行なってこられており、そこがどうしてもフォーカスされがちではあるものの、それだけでは語れない、さおりさんの表現者としての意思やイマジネーションがある。
つぶさに伺ったライフストーリーお届けすることで、「神田さおり」というアーティストから生まれる世界の奥深い部分、あるいは複雑で混沌をきわめる現代の世界において、生きて輝くマインドセットをお伝えできたら何よりである。
会社員としての経験、そしてアーティストとしての道開く
会社員に一度なったからといって決してつまらない日常を送っていたというわけでは無く、そこでもさおりさんらしいセンスを発揮していた。
アパレル業界では、一般的に店舗経験長らく積んでから本社勤務になることが多いが、入社後いきなり本社に務め、「なんかやってくれないか」と持ちかけられる。
毎月本社から全国の店舗に送られる、商品説明・陳列指示書にあたるものを、実際に現場で陳列をする店舗のメンバーがもっと楽しんで仕事ができるよう指示書を全てかわいい漫画に描き起こす等、新しいやり方を色々模索したという。
新店舗が出店する度に全国出張して陳列演出に回り、夢中になってかなり楽しくやりがいをもって仕事をしていた。
ただ、大学卒業間際の時点で、1年後に個展をやらないか、と”Beams B Gallery”から声をかけられており、入社して約一年後に個展を開く了承も会社から得た上でさおりさんは入社していた。
それまで仕事に没頭していたが、いざ個展の時期が近づいてきた。
「『あれ、いつ作品作ればいいんだっけ?』ってなって。時間が無くて。本当に会社から帰ってきて寝ずに作品作りまくって、有給固めて個展を実現できた時に『あれ、こんなに好きだったんだ』って気づいて。
その時に、人生が違う方向に向いている気がして。仕事も楽しいしこのままいけちゃいそうだけど、本当にこれで良かったんだっけ?って立ち止まれて。それで辞表を出す事を決めたの。」
そこでミラクルが起こる。辞表を出した時は、特に与件があったわけでも無く、具体的な展望や後ろ盾も無かったが、最後の業務整理していた時に、電話がかかってくる。
それはパルコに“SAORI庵”を出店していた時のお客さんで、「実は私、音楽会社でアーティストマネジメントの仕事をしていて、今度うちに所属しているアーティストが東芝EMIからデビューするんだけど、そのアートワークをさおりさんにやって欲しいんです」と。
あまりのタイミングの良さに驚いたという。
デビューするアーティストは、林明日香氏。当時、東芝EMIから鳴り物入りでデビューする12歳の女の子だった。
まだ出社日が残っていたさおりさんだったが、海浜幕張のピンクの夕焼け空の中、会社のビルのふもとに音楽会社ミュータントの社長が車で迎えに来てくれて、そのまま車で西麻布の録音スタジオまで向かった。
そこに入ると、ブースの中の12歳の小さな林氏が、ものすごい勢いで歌っていて、あまりの歌声にさおりさんは雷が落ちたような衝撃を受け、ボロボロ涙をこぼしたそうだ。
圧倒的に受けたそのインパクトに自分も何かで答えたくて「紙とペンください!」と言って、何本も鉛筆の芯を折りながら、手を走らせ絵をひたすら描いた。音楽に完全に連れて逝かれて、トランス状態で描くみたいな事が発動したのは其処が初体験だったという。
さおりさんは、アルバムジャケット、MV、ロゴ、そして彼女が着る衣装とボディーペイントまで、デビューアートワークを全て担当。
「それまでやってきた事がそのままピタッとはまったから、ぶわわわんと翼が生えたというか、流れ出る泉。不思議な…。辞表を出したらそれがすぐやってきたって感じ。
自分の魂の声に向き合うのって大事だなって思う。世の中が自分をどう見るか、じゃなくて、私の魂がどう思っているかをすごく大事にしていいんだって、今なら言える。
自分が本当に大好きな事とか、自分の魂が喜ぶ方に行ったら、そこで繋がる人と人生を歩むから、絶対その方がいいと思って。そのための努力はいくらでもする。」
それから、かなり華やかな現場を駆け回る日々となり、“ミュージックステーション”の衣装を現場に行って描くなど、いきなり業界のど真ん中に放り込まれたような感じだったそうだ。それを1年ほど続け、次第にプロジェクトに関わる人数が増えていき、方向性に関しても様々な意見が出るようになって来た中、「ああきっと私、ずっとここにいるの違う気がする」とさおりさんは思い、自らプロジェクトを離れることに。
もう一度またゼロからアーティストとして何がやりたいかを再考し、自身のルーツであるアラビアに向き合うことを決意。
林明日香プロジェクト時のアートワークとは全く異なる、己の中のアラビアの記憶を表現する個展を開催した。
その名も“ ゆ る ゆ る ぐ さ り ”
自分自身のヌードを写真家に撮影してもらい、その写真を和紙にプリント、さらにその上に絵を描く。体を砂漠に見立てた展示。
一度就職し、会社勤めを辞めると同時に林明日香プロジェクトが始動し奔走。そしてまたゼロに戻った時に、誰かの元にワンパーツとして参加するのでは無くて、路自体を自ら創ろうと思い、この展示に踏み切った。




“ ゆ る ゆ る ぐ さ り ” の作品たち
「全員から評価されるわけでは無いし、色んな事も言われるんだけど、本当に自分が今思っている事、感じている事を分かち合えないと死んじゃうと思って。
林明日香アートワークとはまた全然違うものだったから、これをやる事で多くの人が私を嫌いになったらどうしようとかって思った。個展開催前は胃が雑巾絞りされるみたいな気持ちにもなった。でもやってみたら、みんなそれぞれ作品を見る事で思い出したエピソードとか、自分が最近考えてる事とかシェアしてくれて、『ああやっぱり大事』って思った。もちろん、それで連絡を取ら無くなった人とか、離れていったファンとかもいたけど、その時に本当に自分が思っている事を表現するのがあらためて一番大事だと思った。」
“踊絵師”
会社辞めて大きなプロジェクトに関わり、それでまた25歳でゼロに戻って、さてどうする、となった時に「本当に好きな事をやりたい!」という強い思いに駆られた。
「体全部を使って描きたい!踊りながら描きたい!って模索してる中、ふと踊絵師って言葉が降りてきたんだよね。踊りながら描くその瞬間を求めて求めて、今に至る。
そのプロセスを経て『変わらないのは、変化し続けることだけ』と心から言える。他人から理解される為に自分を固定する必要は全く無い。世の中的にわかりやすい肩書きで自分を語る為に自分をとどめちゃダメだって。自分は変化が楽しいし怖く無い、変化し続ける事だけが永遠に変わらないから、その自分として世界と向き合っていこうと思ってます。
変化する人は、何かを達成する事でもう大丈夫だって思ってなくて、常に今この時の真ん中が何なのかを探していて、その道中で分かち合える人が必ずいて。そんなエネルギーの最中で紡ぎ出される何かがきっと、色んな人に届くというか。みんな迷ってるから。
なんでこんなわざわざ悩むんだろうとか、なんでわざわざこれまで築いてきたものを壊すんだろうとかって自分に対して思うけど、きっとおそらく多くの人がそこにぶち当たっていて、そこのためにもやっぱ表現は在るかもって。生きるっていう事に対して、生ききるっていう表現として。LIFE ALIVE。複雑で簡単じゃないことで。アートっていうものに、文学も身体表現も音楽表現も美術も全部入っているとして。生きるっていうことは、食事をして睡眠をするだけではないから。魂を生きるっていう事に対して、勇気を持ってそこに集中する為にやっぱりアートがあると思う。」
そんな思いで、“踊絵師”という名が生まれた。
自身が“踊絵師”というワードが世に浸透した実感を持ったのが、2013年のNissanのカレンダーのお仕事。さおりさんは、1月から12月まで全ての月のアートワークを担当。
広大なスタジオ空間に日産の車を置き、床から壁まで駆けめぐって空間一面に巨大な絵を描く。描き上げた絵と車とさおりさん自身を納めた写真がカレンダーのアートワークに起用されたと同時に、製作中の様子を収録したWEB CMもリリースされた。その動画がYOUTUBEを通して広く行き渡り、”踊絵師-おどりえし”という言葉が浸透。
Nissanカレンダーの製作をした2012年が、会社を辞めてアーティストとして活動を始めた10周年だった事もあり、日産プロジェクトはアーティストとして10年間で培ったものを全方向に注ぎこんだ集大成となり、かなり思い入れが強い作品になったという。それまで踊絵師の表現を共に創造してしてきてくれた大切なクリエイター仲間にもプロジェクト参加してもらい、絵を描く事はもちろん、コンセプトメイク、衣装、ヘアメイク、音楽、撮影などトータルでプロデュースした。
そしてこの映像が、A’DESIGN AWARD (Milan Italy)の Graphics and Visual Communication Design部門最高賞プラチナ受賞。人生初の受賞となった。

実際のNissanのカレンダー 


アートワークとさおりさん 
“踊絵師”というと、「踊りながら絵描くのね」と安直に理解されそうだが、現場のエネルギーに感覚を委ねるままにある意味トランス状態にて身体が動き、踊りとなり、その踊りの軌跡として生まれる色彩やタッチが絵と成る、という極めて自然な流れで生まれたスタイルだということで納得感がある。
アートワークのダイナミックさ、細密画、そして踊絵師
様々な作品を残すさおりさんだが、やはりダイナミックな作品が印象的。ただ元来からそうだった訳では無いという。
「ドバイの頃ずっと絵を描いてた時は、とにかく細かい模様を描くのが好きで。日本からお土産で貰った千代紙の模様を模写してみたり、細密に細密に追い込んで描くのが気持ちよくって。あと日本の漫画に飢えてたから漫画の模写も良くやった。ラムちゃんとか、らんまとか超上手に描ける(笑)。小学生の頃は漫画家目指してたし。
鉛筆でペンで緻密に追っていくのが最高に快感、そういう自分が元々いたの。それが音楽との遭遇に突き動かされて、身体全部使って描く!という踊りに繋がっちゃって、ほんと突然発動したんだよね。
そこから十五年くらい無我夢中で踊り描いてきて、一周りして最近はまた細密に描く気持ちよさが戻ってきてるの。」
ここで伺った、さおりさんの思うアートワークと人々との関わり方に関する考え方がとてもおもしろかった。
「身体全部使って大画面を踊り描くことも人生を通してやっていきたいんだけど、なんか最近はそのアフターな感じとか、前夜祭とか後夜祭なバイブスに寄り添う作品も作りたくなってきて。大事なステージのために国外遠征行ったりする時に、本番を間近に控えたホテルの時間とか結構最高だなって思ってて。そのタイミングで一緒にいる人たちってものすっごく大事な人たちで。
その人たちとお互いを祝福しあって過ごしている最中に、なにを聴きたいとか何を肌に纏いたいとか、何を食べたいとか、どんなアートを愛でたい、っていう所に、今すごく興味があって。」
“踊絵師”として舞台に立ち絵を描く際は「いってまいります」とある種結界を超え、無我の境地でトランス状態となり、自分のコントロール下で思考して描くというより、自我を超えた大いなるものに突き動かされて描くという。
一方で今さおりさんが関心を寄せるアートワークの形態に関してこのように語る。
「最近思うのが、もっとごくごく“私”として、大切な本番を迎えるその前やその後にそばに居てくれるモノも創りたいなって。
もっともっと個人的なこと。うっとり眺める小さな額に入った絵もやりたいし、そのとき一緒に聴きたいもの、たとえば夏の終わりにピンクの空を眺めながら永遠ループして愛でたい音楽も創りたいし、その瞬間にふと寄り添える言葉も書きたいし。うっとりと、そばに在る、人生のCHILL時間に味わう表現やりたいって最近思ってる。そういう芽生えが ”今”な感じ。」
―やっぱりパンデミックによる生活の変化も関係しますよね。なんでもない一日一日のことを考える事って今まではあまり無かったなって思います。
「喜びを分かち合いたいってのが私の真ん中にあって。ほっとした時間に分かち合うものもやりたいなって最近は思う。この10数年、無我夢中で我を忘れてうわぁぁーーーっと踊り描き続けてきた。
そんな最中コロナが為にアートパフォーマンスの現場から半年離れる事になって。ゆっくり”私”として考える余裕を持てて。踊絵師としてのあの圧倒的な瞬間、そのエネルギーの核心にこそ極上のビフォアとアフターはあるなと。言うなれば”解放”を包みこむ”癒し”。全て人生の物語だから、そこも大事にしたいって、やっと気付いたという(笑)」
山場となる時間において放出する熱量がすさまじいさおりさんだからこそ、その前後の時間や空間、プライベートでパーソナルな部分を大切にしたいという思いが生まれたのだろう。
パーティが生きるヒント
これだけ分厚くさおりさんのライフヒストリーや表現活動について記してきたが、
さおりさんは自分の根本を“ PARTY野郎 ”だという。
父親の仕事の関係で幼少期イラクのバグダットで暮らしたわけだが、その当時は、イラン・イラク戦時下。
そんな中、当然現地にいる日本人は極めて少なく、だからこそ互いの結びつきも強く、助け合って生活していたという。
父親の勤める会社の日本本社からイラクの様子を視察に来る方がいた場合、さおりさんの家でもてなしていたそうだ。
手に入る少ない食材で母親が手料理を振る舞い、父親が客人をもてなし、両親が力を合わせてホームパーティを切り盛りしている。
また時には近所のアラビア人一家と合同ホームパーティを行い、宴のラストは腰に紐を結びアラビックダンスに興じ大盛り上がり。
そんな最中でさおりさんは育った。

アラビア時代のホームパーティの様子 
「根っからのパーティ野郎だよね(笑) それだなぁって、最近つくづく思う。
なんだろう、その、音楽とか絵描きとか、ダンサーとか、アートとか、エンターテイメントとか、そういうジャンル分けって自分の中ではあんまり関係なくて。” PARTYをつくる “っていうことが、私の根っこなんじゃないかって、最近思ってます。」
また、さおりさんは、PARTYを “光の持ち寄り” と表現する。
「国内外の現代アートの現場だったり、フェスなどミュージックシーンだったり、企業とのコラボレーションだったり、様々な現場に関わらせてもらいながら感じるのは、ジャンル関係なく、やっぱり一番人生の宝となるのは出逢いなんだってこと。出逢いの分、想像もしていなかった扉が開き続けるし、やりたい事、できる事の変化も進化も続く。喜びもあれば悲しみもあって、時には悔しさ不甲斐なさもある。
だけど出逢いによって魂は現在進行形で磨かれ続ける。出逢いを通して常に己を知る。今この瞬間の魂の声に素直になって、それを悦びに満たしてあげるのが一番大切で。
これまでは自分の光ってなんだ、って事を一生懸命模索してきたけど、今は自分の光はちゃんと在る、そこを信じられる様になった。
そして光を繋げて響かせあえる人と、光の輪を広げていきたいなぁって。その美しさを一緒にうっとり分かち合いたいなぁって。
そうやって生きて生きたい。今は本当そこに集中している。光の持ち寄りがPARTYだとして。」
様々な避けようのない環境の変化に多くの人が翻弄される中、さおりさんが語ることは、ある種、アーティスト活動をする人たちのみならず、あらゆる生き方をする人々に向けての、人生を紛れもない自分の人生として楽しむためのヒントといえるのではないか。
「コロナのせいでというかお陰でというか、己を語るときの後ろ盾とか仕組みは、今後どんどん皆それぞれ変わっていくだろうし。でも今のこのタイミングこそ、チャンスだとも思う。人生は有限だから、魂が嬉しくて悦ぶ仲間探しをした方がいい。変化し続けることは何にも怖く無い。自分らしく大好きなことで、誰かの役にも立てて、生活のためのお金も得られることって、誰しもに絶対にあると思う。
きっとみんな手放しでハッピーな人なんて誰もいなくて、自分にその生き方を許す事からなんだと思う。
自ら光の方へ辿り着いて欲しいなぁって願うよ。」
ただただ才能があるアーティスト、というだけであれば、その表現を届ける先の人の心情を想像することはときに難しいのではないかと思う。
生きることをやめたくなるほど苦しみ、それを乗り越えて心から生きていてよかったと実感しながら表現活動をするさおりさんだからこそ、人の心理に深く語りかける芸術を創り出すのだろう。

〜 END 〜
Oct 10th / 2020
Interview & Writing: Jasmine
この投稿へのトラックバック
トラックバックはありません。
- トラックバック URL
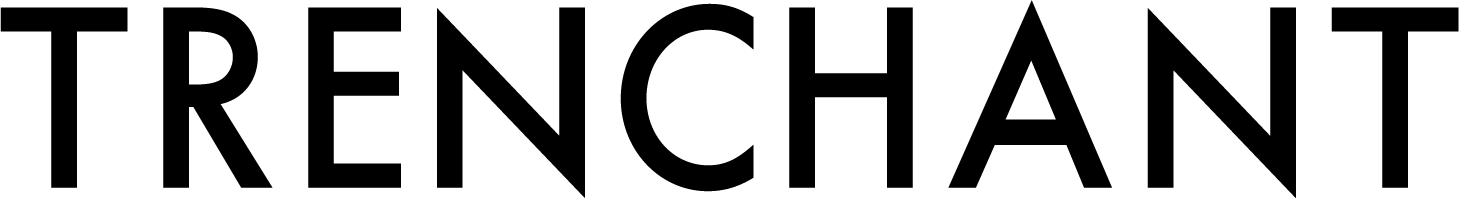
この投稿へのコメント